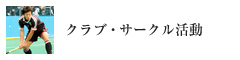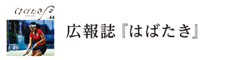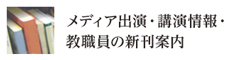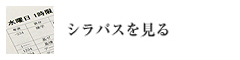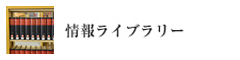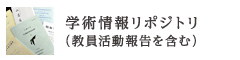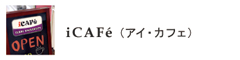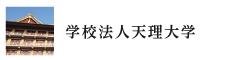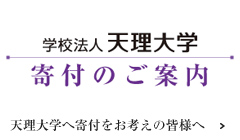《公開講座記録》【ことばと文学】第1回 詩のかたちの歴史
第1回
●2022年7月30日(土) 午後1:30
●テーマ: 詩のかたちの歴史
●講師 浜田 秀(国文学国語学科 教授)
●2022年7月30日(土) 午後1:30
●テーマ: 詩のかたちの歴史
●講師 浜田 秀(国文学国語学科 教授)
内容

現代、「詩」という言葉でイメージされるのは、どのようなテクストであろうか。代表的な「詩人」は例えば高村光太郎、萩原朔太郎であり、その「詩」は通常の日本語で書かれ、改行を持つ物としてイメージされるのではなかろうか。
しかし、このようなジャンルにまつわる常識は、近代のものに過ぎない。江戸時代以前は「詩」は中国語による古典の定型韻文、いわゆる「漢詩」を指すものであったが、この「漢詩」という言葉もまた近代の産物である。そして、そこに改行は必要とされなかったのである。
この移行は二つの革命を経ている。一つは1882年(明治15)の『新体詩抄』の出現、いま一つは1907年(明治40)の口語自由詩の出現である。
第一の革命、『新体詩抄』は、二つの大きな事を行った。ひとつは日本語の韻文ジャンルに改行の形式を導入したことであり、いま一つはこの新しい五七調文語体のジャンルに「新体詩」と命名したことである。
第二の革命は川路柳虹の「塵溜」が濫觴とされる。ここにおいて、「新体詩」は五七調から自由になると同時に、詩と他を区別する定型というよりどころを失うことになった。となるとのこされた属性は「改行」のみになる。ここに改行と詩のもつれた関係が生じることになった。
柳虹のあとを追って口語自由詩を試みた相馬御風の「痩犬」(1908年(明治41)6月)に対して、ただちに折竹蓼峰は改行を取り去って、「これが詩か」と罵倒した。これを受け生田長江は「今の口語詩は、縦のものを横に並べたに過ぎない」と揶揄した(1908年(明治41)11月)が、これらは口語自由詩一般の批判であった。
1922年、北原白秋は民衆詩派の白鳥省吾の作品、「森林帯」の改行をとりさり、これが詩か、と罵倒した。ここには、折竹蓼峰のレトリックが反復されているわけだが、すでに口語自由詩のステータスは確立しており、その上での価値を弁別する手法として議論されている。そこには「単なる行分けした散文が詩であるはずがない」という認識が前提となっている。
1917年ごろ、朔太郎は自らのノートに、日本の評論家は横に行を分けて書いたものが詩と思っている、と書きのこしている。この表現は長江の表現を受けているが、朔太郎はこのレトリックを手がかりに、詩の本質を考え続けた人物である。1928年の『詩の原理』を経て、朔太郎は晩年にも「似而非詩の真偽を鑑定するには、行分けを縦書きに直してみるに限る」と同様のことをしている。
しかしながら、近年の議論は、朔太郎や白秋のように、かならずしも詩と非詩とを単純に分けるものとしてこのレトリックを利用していない。詩とは何かという問題が解決したわけではないが、それが真剣に問わねばならない問題だと感じられなくなったのである。
詩と改行をめぐる議論にあって、注目すべきは余白を沈黙と関係づけて取りあげたものである。詩には、沈黙をしめす余白が必要だと考えるのである。北川透は『詩的レトリック入門』で、紙の上の余白は沈黙のメタファーとして機能すると主張し、いわば汎余白論とでもいうべきものをうちたてた。この立場は増成隆士や野村喜和夫にも受け継がれているが、遡れば北川冬彦の言説にも同様のものがある。
ただし、彼らの言葉は詩人、評論家としてのものであり、これをそのまま言語理論とすることはできない。我々が常識的に、詩と非詩とをどう弁別しているのか、というカテゴリー認知の問題と、詩はどうあるべきかという詩的価値の問題を区別する必要がある。また、改行が余白を生むことはわかりやすいが、改行を持たない散文詩がなぜ詩にカテゴライズされるのかも考えるべきであろう。
しかし、このようなジャンルにまつわる常識は、近代のものに過ぎない。江戸時代以前は「詩」は中国語による古典の定型韻文、いわゆる「漢詩」を指すものであったが、この「漢詩」という言葉もまた近代の産物である。そして、そこに改行は必要とされなかったのである。
この移行は二つの革命を経ている。一つは1882年(明治15)の『新体詩抄』の出現、いま一つは1907年(明治40)の口語自由詩の出現である。
第一の革命、『新体詩抄』は、二つの大きな事を行った。ひとつは日本語の韻文ジャンルに改行の形式を導入したことであり、いま一つはこの新しい五七調文語体のジャンルに「新体詩」と命名したことである。
第二の革命は川路柳虹の「塵溜」が濫觴とされる。ここにおいて、「新体詩」は五七調から自由になると同時に、詩と他を区別する定型というよりどころを失うことになった。となるとのこされた属性は「改行」のみになる。ここに改行と詩のもつれた関係が生じることになった。
柳虹のあとを追って口語自由詩を試みた相馬御風の「痩犬」(1908年(明治41)6月)に対して、ただちに折竹蓼峰は改行を取り去って、「これが詩か」と罵倒した。これを受け生田長江は「今の口語詩は、縦のものを横に並べたに過ぎない」と揶揄した(1908年(明治41)11月)が、これらは口語自由詩一般の批判であった。
1922年、北原白秋は民衆詩派の白鳥省吾の作品、「森林帯」の改行をとりさり、これが詩か、と罵倒した。ここには、折竹蓼峰のレトリックが反復されているわけだが、すでに口語自由詩のステータスは確立しており、その上での価値を弁別する手法として議論されている。そこには「単なる行分けした散文が詩であるはずがない」という認識が前提となっている。
1917年ごろ、朔太郎は自らのノートに、日本の評論家は横に行を分けて書いたものが詩と思っている、と書きのこしている。この表現は長江の表現を受けているが、朔太郎はこのレトリックを手がかりに、詩の本質を考え続けた人物である。1928年の『詩の原理』を経て、朔太郎は晩年にも「似而非詩の真偽を鑑定するには、行分けを縦書きに直してみるに限る」と同様のことをしている。
しかしながら、近年の議論は、朔太郎や白秋のように、かならずしも詩と非詩とを単純に分けるものとしてこのレトリックを利用していない。詩とは何かという問題が解決したわけではないが、それが真剣に問わねばならない問題だと感じられなくなったのである。
詩と改行をめぐる議論にあって、注目すべきは余白を沈黙と関係づけて取りあげたものである。詩には、沈黙をしめす余白が必要だと考えるのである。北川透は『詩的レトリック入門』で、紙の上の余白は沈黙のメタファーとして機能すると主張し、いわば汎余白論とでもいうべきものをうちたてた。この立場は増成隆士や野村喜和夫にも受け継がれているが、遡れば北川冬彦の言説にも同様のものがある。
ただし、彼らの言葉は詩人、評論家としてのものであり、これをそのまま言語理論とすることはできない。我々が常識的に、詩と非詩とをどう弁別しているのか、というカテゴリー認知の問題と、詩はどうあるべきかという詩的価値の問題を区別する必要がある。また、改行が余白を生むことはわかりやすいが、改行を持たない散文詩がなぜ詩にカテゴライズされるのかも考えるべきであろう。